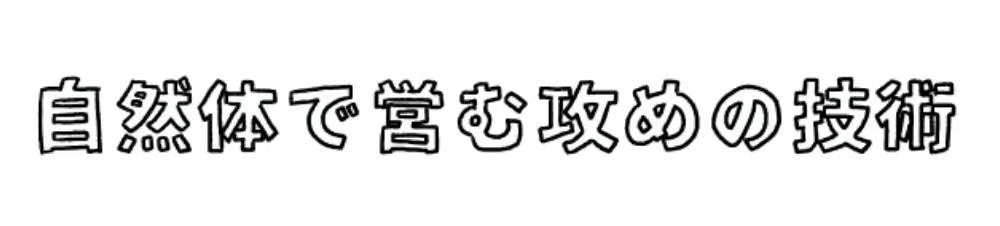AI×メールで売り込みゼロの『自然体ビジネス』設計士、長嶺圭一郎です。
さて、今日は小規模でビジネスをされているあなたが、もしかしたら一度は頭を抱えたことがあるかもしれない「オンラインコミュニティ運営」についてお話ししようと思います。
「せっかく作ったコミュニティが、なんだか盛り上がらない…」「もっと投稿を増やさなきゃダメなのかな?」なんて、一人でプレッシャーを感じていませんか?僕もその気持ち、すごくよく分かるんですよね。
この記事の要約
- 「盛り上げなきゃ」は思い込み:多くの運営者が陥るプレッシャーの危険性と、その乗り越え方。
- 「静か」は自然な姿:参加者の9割が見る専門(ROM専)なのは自然の法則。「90-9-1の法則」を解説。
- 心地よい場の作り方:無理な盛り上げ方をせず、満足度を高める具体的なオンボーディングやKPI設計のコツ。
- 3年間の実例:僕が実践してきた、100人超のコミュニティを「ぬるま湯」の心地よさで育てた3つの秘訣。
コミュニティ運営、「盛り上げなきゃ」の呪縛に疲れていませんか?
「シーン…」と静まり返るコミュニティの気まずさ、身に覚えありませんか?
あなたが何かを投稿しても、いいねが数件、コメントはゼロ…。そんな状況が続くと、「私のコミュニティ、失敗なのかな?」なんて不安になりますよね。
でも、考えてみてください。人数が30人、40人と増えてきたコミュニティの雰囲気を、運営者一人の力で変えるのって、実はものすごく難しいことなんです。
これって、少し極端な例えかもしれませんが、学校のクラス運営に似ていると思うんですよね。一度「学級崩壊」してしまったクラスを、先生一人の力だけで立て直すのが困難なように、コミュニティも一度固まった雰囲気を変えるのは至難の業なんです。どうでしょう? 少し想像がつきませんか?
急成長の裏に潜む「組織崩壊」のリスク
「それなら、一気に人数を増やしてしまえば活気が出るかも!」そう考える方もいるかもしれません。でも、実はそれ、ちょっと危険なサインかもしれないんです。
飲食店のチェーンが急拡大した結果、各店舗のサービス品質を保つ人材が育ちきらずに、組織全体がガタガタになってしまった…なんて話、聞いたことありませんか?
コミュニティも同じで、その場所ならではの「空気感」や「文化」が育つ前に急激に人数が増えると、価値観のズレが生じたり、当初の目的とは違う方向へ進んでしまったりすることがあるんです。焦って拡大した結果、誰も居心地の良さを感じられない場所になってしまったら、悲しいですよね。
「静かでも大丈夫」を裏付ける、コミュニティ運営の原則と実践テクニック
「でも、やっぱり反応が少ないと不安…」そう感じますよね。そこで、まず知っておいてほしい大原則があります。
ROM専が多いのは当たり前!コミュニティの「90-9-1の法則」
実は、オンラインコミュニティには「90-9-1の法則」という有名な法則があります。これは、参加者のうち90%はROM専(見る専門)で、9%はたまに反応する人、そして積極的に投稿するのは残りの1%だけ、というものです。
つまり、あなたのコミュニティが静かなのは、失敗だからではなく、ごく自然な状態である可能性が高いんです。この法則を知るだけで、少し肩の荷が下りませんか? 無理に全員を巻き込もうとするのではなく、この前提で心地よい場所を設計することが大切なんです。
「静かなコミュニティ」だからこそのKPI設計とオンボーディング
この法則を踏まえると、見るべき指標(KPI)も変わってきます。
- 見るべき指標(KPI)の例:
- 投稿数やコメント数よりも「継続率」や「満足度アンケートの結果」を重視する。
- イベントの参加人数だけでなく、参加後の「熱量の高い感想」に注目する。
- 新規メンバーを温かく迎えるオンボーディングのコツ:
- 最初の挨拶は、誰もが書きやすいように自己紹介テンプレートを用意する。
- 「まずは、この『くだらないこと報告スレ』にいいねを押すことから始めてみてくださいね」など、参加へのハードルが低い最初のステップを優しく案内する。
「盛り上げ」ではなく、「居心地の良さ」を軸に設計することで、コミュニティは静かでも着実に育っていきます。
▼ コミュニティ運営とメルマガについて、もっと詳しく知りたい方へ
メルマガも読者さんとの大切なコミュニティの一つです。読者参加型のメルマガ運営のヒントはこちらの記事で詳しく解説しています。
100人超えでも心地よい「ぬるま湯コミュニティ」運営の3つの秘訣
「じゃあ、具体的にどうすればいいの?」と思いますよね。大丈夫です。僕が主宰するコミュニティ『ゼロリス』は、おかげさまで100名以上の方に参加いただいていますが、実は、皆さんが想像するような「いつもワイワイガヤガヤ」したコミュニティではないんです。
むしろ、かなり「静か」な方だと思います。それでも、ありがたいことに、参加者の皆さんからは「満足度が非常に高い」と言っていただいています。あるメンバーさんからは「ゼロリスの空気感は、ぬるま湯のようで心地よいです」なんて嬉しい言葉をいただいたこともあるんですよ。
▼ 実際のメンバーさんの声はこちら
ゼロリスの「ぬるま湯」のような空気感が、参加者にどんな変化をもたらしたのか、リアルなインタビュー記事をぜひご覧ください。
ここでは、そんな僕が3年間で気づいた、無理せず心地よいコミュニティを作るための3つの秘訣をお話ししますね。
秘訣1:無理に盛り上げない勇気!「ロム専大歓迎」が作る最高の居心地
少し気恥ずかしい告白ですが、僕自身、他の人のコミュニティに参加したとき、そんなに頻繁に投稿するタイプではないんです。静かに皆さんの投稿を眺めたり、提供されるコンテンツで学んだりするだけで、十分に満足できちゃうんですよね。
だから、僕の『ゼロリス』では、「ROM専(ロムせん:見る専門)大歓迎!」ってはっきり伝えています。「投稿しなきゃ」というプレッシャーを感じずに、自分のペースで関われる場所にしたかったんです。
すると、面白いことに、「ビジネスのモチベーションが落ちて、他の発信は全部見なくなったけど、ゼロリスだけはずっと居心地が良くて、い続けられました」と言ってくれる方が現れたんです。人間誰だって、ずっと全力疾走はできませんからね。ちょっと疲れた時でも安心して羽を休められる。そんな場所があるって、なんだか心が晴れる瞬間じゃないですか?
秘訣2:「くだらないこと報告スレ」に学ぶ、”余白”の大切さ
コミュニティの運営者だからって、常に完璧でいる必要はないと思うんですよね。
僕もゼロリスでは、「今日、こんな失敗しちゃいました…」なんて、表ではなかなか言えないような弱音を吐いたりします。そういう人間らしい部分を見せることで、なんだかメンバーさんとの距離が縮まる気がするんです。
ちなみに、ゼロリスには「くだらないことを報告するスレ(有益情報現金!)」という場所があるんですが、実はここが一番コメントで盛り上がっていたりします(笑)。こういう一見無駄に見える「余白」や「ツッコミどころ」こそが、メンバーさんが気軽に発言しやすくなる、大切な潤滑油になるのかもしれませんね。
秘訣3:焦りは禁物。3年かけてじっくり育てるコミュニティの土台
僕の『ゼロリス』は、プレオープン期間も含めると、もうすぐ丸3年になります。そして、2025年の4月16日に、参加者が100名を超えました。最初は、僕のことを本当に好きでいてくれる「濃い」メンバーさんが20人ほど集まってくれました。
この、少人数の時期に作られた「空気感」が、今の100人超えのコミュニティの土台になっていると、僕は確信しています。
だから、もしあなたが今、参加者が少ないことに悩んでいるとしても、焦る必要は全くありません。むしろ、その少人数の期間こそが、あなたのコミュニティの「文化」を醸成する、かけがえのない時間なんです。一歩ずつ、じっくり育てていく。この感覚、大切にしてみませんか?
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 静かなコミュニティでも、本当にビジネスは成長しますか?
A1. はい、成長します。「90-9-1の法則」が示す通り、活発な投稿数=満足度ではありません。大切なのは、少数でも熱量の高いファンが生まれ、その方々がサービスの購入や紹介をしてくれることです。「継続率」やお客様の声を指標にすれば、静かでも着実な成長を実感できます。
Q2. イベントを企画しても人が集まりません。どうすれば良いですか?
A2. まずは参加のハードルを下げてみましょう。例えば、「顔出し不要OK」「聞くだけ参加OK」のオンライン勉強会や、簡単なアンケートに答えるだけの企画などです。参加しやすい小さな成功体験を積み重ねることが、次の参加へと繋がります。
Q3. 運営者の私が疲れてしまいました。続けるコツはありますか?
A3. 完璧を目指さないことです。この記事で紹介したように、「くだらない投稿」で息抜きをしたり、時にはメンバーさんに「助けてください!」と頼ったりするのも一つの手です。運営者自身が「自然体」でいることが、コミュニティを長続きさせる最大の秘訣です。
あなたのコミュニティも「自然体」で成長できる
いかがでしたでしょうか?コミュニティ運営って、派手なイベントを企画したり、常に投稿を促したりすることだけが正解じゃないんです。
むしろ、運営者自身が自然体でいて、参加者が安心して「ただ居る」ことを許される場所。そんな「心の安全基地」のような空間を作ることこそが、長く愛されるコミュニティへの一番の近道なのかもしれません。これは、日々の「心の筋トレ」みたいなものかもしれませんね。
▼ リストマーケティングについて、もっと詳しく知りたい方へ
コミュニティ運営は、顧客との深い関係を築く「リストマーケティング」そのものです。僕が実践する具体的な手法はこちらの記事で詳しく解説しています。
もし、今日の話を聞いて、「リストマーケティングや、もっと深いコミュニティ運営について知りたいな」と思っていただけたら、ぜひ僕の公式メルマガに登録してみてください。
今なら特典として、2時間42分にも及ぶセミナー動画「全販売者がすぐ始めるべきリストマーケティング7つの優位性」を無料でプレゼントしています。 あなたのビジネスを、もっと自然体で、もっと楽しくするヒントがきっと見つかるはずです。
参考資料
- Participation Inequality: The 90-9-1 Rule for Social Features (Nielsen Norman Group)
- 有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 (Google 検索セントラル)
無料セミナーでリストマーケティングを学ぼう!!